先覚者・文化財


 先覚者・文化財
先覚者・文化財  先覚者・文化財
先覚者・文化財  先覚者・文化財
先覚者・文化財  1302大井五郎満安の墓
1302大井五郎満安の墓  0102日新堂跡
0102日新堂跡  1102斎藤寅次郎が育った家(跡地)
1102斎藤寅次郎が育った家(跡地) 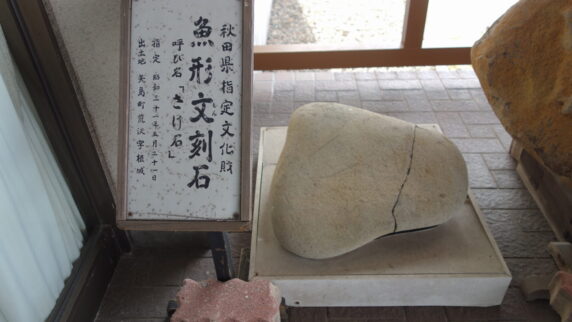 1601矢島郷土資料館
1601矢島郷土資料館  先覚者・文化財
先覚者・文化財