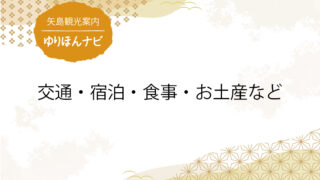概要
矢島町舘町の大井家は、江戸時代中期の宝暦年間(1750年代)より酒造業を営んでいた家系で、藩財政にも関与していた旧家です。
特筆すべき事として、天保飢饉の際には、窮乏する藩財政の立て直しの一環として、酒田本間家との借財交渉において、陣頭指揮の立場でした。
時代が下った先の大戦時には、戦線に送られた男手の不足を補うこととなった母親の負担軽減のため、私財を投じ、託児所の設置運営に努めています。現在の矢島保育園の前身です。
時代が変わった戦後には、一族の中から衆議院議員、矢島町長を輩出しています。
一方、大正5(1916)年に竣工した本家屋は、向かって左側が町屋造り、右側が武家風造りとなっており、二形式が併存しています。
主な材は、柱(ちゅう)梁(りょう)および床は、地元産のケヤキ、床柱等は、黒檀(こくたん)、鉄刀木(たがやさん)が用いられ、これ以上の物は求めがたい極上の材で構成され、当家屋の特徴ともなっています。
そんな家屋でしたが、昭和48年から平成10年までの20年余の間は、主不在の状況に陥り、現建物は、廃屋寸前の惨憺たる状況となりましたが、これと同年数を修復に努めた結果、ほぼ創建当時の状態に復することができたと思います。そして、近代の商家住宅として、平成16年に国登録有形文化財に指定されています。
尚、通年にわたり生活の場としておりますので、住宅内部の公開にはお応えできないのが現状ですのでご了承ください。
音声ガイド(音声のみ)
サイズ 1Mb前後動画(音声ガイド付)
サイズ 10Mb前後画像



詳細
大井家は讃岐生駒家家臣大井覚右衛門から分家して、藩政期に酒造業を営み御用酒屋として生駒家に仕えました。
明治以降は多くの政治家を輩出し、10代目直之助は、5代目矢島町長務め、後に衆議院議員となりました。また弟の五郎も矢島町長を務め兄弟揃って町長を務めた矢島の名家です。
大井家住宅の主屋は寄棟造りで、大正2年から4年を費やして建築されました。近代富裕層の住宅の様子を現代に伝える近代和風の建築物として平成16年には国登録有形文化財に指定されております。
平成16年11月8日国登録有形文化財(建造物)大井家住宅主屋
大井家当主からの説明
●以下の論稿等は、大井家当主 大井 益二氏が作成したものですが、矢島町郷土史と当家の接点についてのものが主体です。
1 舘町大井家にかかわるQ&A
大井 益二 ●当家(以下舘町大井家とも呼称)に来られた方々から、よく受ける質問があります。
これらの質問をQ&Aの形式で説明したいと思います。
(1)由利十二頭・大井光安と当家とのつながりについて
Q:戦国時代に由利地方に蟠踞していた由利十二頭の一人大井五郎光安と、舘町大井家はどの様な繋がりがありますか。
A:家伝では当家の祖は大井光安(矢島満安)となっています。
江戸中期より商家でありながら、当家は公然と大井姓を用いており、伝えを肯定しているように思えます。
江戸時代の生駒藩の中核は光安の遺臣の子孫ですから、光安と無関係な人物が、大井を公称する事は、きわめて考え難いからです。
また裏付ける資料としては、後出文書に示す文書が伝承されています。
この書状の発信者は山形県庄内を領していた大宝寺義氏(天正11年没)で、受信者は大井光安で、書状では「矢島六郎五郎」となっております。
大意は「正月に白扇を頂きありがとう。このうえは『上』に、よしなに伝えます」です。白扇が何を示すのかは不明ですが、それをもって「上によしなに伝える」わけですから、両者にのみ分かる重要事項であると推察されます。
そして『上』にあたる人物としては、行間に漂う義氏の余裕から、彼が人質時代に薫陶を受けた関東管領職・上杉謙信ではないかと推察されます。
仮にそうだとすれば本書が作成されたのは謙信存命中の天正6年(1578)以前となります。
江戸時代のいつの頃からは判然としませんが、この書状を当家では正月に奉安する事が、しきたりとなっています。
なお解読は複数の東北大学史学関係者により行なわれました。
(2)生駒藩重臣・大井光長と舘町大井との関係について
Q:生駒家譜の宝永年間の記載に、「大井光長」の名が重臣としてその名が見えますが、舘町大井家との関係はありますか。
A: 生駒家譜に四代正親時代(元禄15年~宝永3年の3ヵ年半)の記録に「江戸・生駒家菩提寺・海禅寺御墓前、献灯篭記名」の項に、大井光長の名が、金子、小助川、高柳、佐藤、相庭、河内らの、光安股肱の臣の子孫の氏名に先立ち刻されていたことが記されています。
この事は士分である大井光長が、元禄期まで生駒家の有力家臣として在籍していた事を示しています。
しかし武士としての大井氏はこの光長を最後に以後公式文書に一切登場しません。
入れ替わるようにほぼ同時期に商家大井家が塩の専売権や酒造権の付与などの、藩の全面的な支援のもとで、突如出現しております。
そして藩の指示により系図や家譜等の出自に関わるものを、光長本家のみならず分家所蔵の物まで強制的に集め、護摩炊くしたとの伝えがあります。
藩としては武家大井と商家大井とは全く無関係とすることで、大井家の存続を認めたものとおもいます。
関ヶ原の役に上杉方につき、反徳川行動をとった大井氏の縁につながる者を藩の重臣として処遇していた事を憚ったものと想います。
丁度同時期に江戸藩邸では、讃岐高松より矢島に左遷された時の当主・生駒高俊の暗愚ぶりが記された由緒書が藩主導のもとに作成され、京の菩提寺に、これ見よがしに置かれました。
つまり左遷は幕府の恣意ではなく、ひとえに高俊が暗愚によるものですといっているわけで、国許矢島、江戸藩邸ともに軌を一にして、幕府への尊崇行動をとっていたわけです。
さりとて金子、小介川高柳等の遺臣の子孫たちは、主筋の大井家の衰亡を座視する事はできず、苦肉の策を講じたものとおもいます。私は光長あるいはその嫡子は、商家初代の大井傳之亟とは、同一人物と考えております。
さらに藩は大井縁の寺(法華宗)を新たに開山するなど、中世大井氏と舘町大井家の繋がりを断つべく腐心しておりますが、先祖の中には「我が遺体は光安公墓所(曹洞宗)に葬るべし。子孫違背するべからず」と、遺書により厳命した者もいますが、実行されたかどうかは不明です。
明治以降の子孫はこのひそみを心の片隅においていたようで、戦時下の昭和18年の光安墓碑の改装事業にも、工事費のかなりの部分(一千円)を寄進しております。
なおこの時の発掘で、光安のものとみられる前頭部に刀痕がある大ぶりの頭蓋骨と大腿骨が出土しています。
(3)舘町大井家の家紋について
Q:仮に舘町大井家が光安の系統とすれば、武田→小笠原→信濃大井→矢島大井と、繋がる系統ですので、舘町大井家も紋は武田菱になると思われますが、なぜ「四ツ目結」なのでしょうか。
A:舘町大井家には人為的に作られたと考えられる本家があります。元々の姓は佐々木で、出自は讃岐高松で、祐筆の家柄であったと伝えられています。
矢島に来てからは、藩重臣の菅原覚左衛門の家人となりました。
そして覚左衛門の命により、由緒ある大井姓と主の一字を賜り「大井覚右衛門と称しましたが、武士身分ではなかったようです。
極めて不自然な事ですが、自前の経済力が伴わない新大井家ですが、次の世代で、早々に四家に分かれました。その一派が当家です。
従って、家紋も佐々木氏の紋である「四つ目結」となり今日に至っています。
このことは矢島大井氏と商家大井家が無関係と思わしめるための、一連の操作のひとつであったと思います。
なお天寿酒造・大井家、当家の文政時代の分家で、上記とは関わりはありません。
(4)庭園について
Q:舘町大井家の西側庭園が、織田信長に滅ぼされた朝倉義景により建てられた諏訪館の庭園と似ていると聞いておりますが、繋がりがあるのでしょうか。
A:両者の写真(後出)を先ずご覧ください。
正徳年間の古地図を見ますと、庭園の箇所には家屋がありました。
大井家では是が非でもその土地が必要であったとみえ、現在も舘町に住まいしている方の先祖から、享保年間い購入しております。
その執着ぶりから、そこには先祖と繋がる庭園の遺構があったのではないかと私は考えております。
庭園の完成は建物竣工の一年後の大正6年です。
この時の工事写真には土のみの地表しか映っておりませんでした。もしこの時に表土を除き、遺構の有無を確認し撮影しておれば以下の推測は不要であるのですが残念ながら、当時を知る人もすでにおりませんので以下推論します。
ところで北陸からは信長に追われた一向宗門徒が多数秋田方面に移住した事は、関ケ原の役以前に松ヶ崎に、浄土真宗二ヵ寺が存在したことからも明らかです。役後に入部した楯岡豊前の守の治下に、本荘城下に二寺とも移転しております。
命からがら由利に辿り着いた門徒は塩焼きをして細々と糊口をしのいでいましたが、そんな様子を聞き、自陣に引き入るため、光安は門徒の中に庭師がいる事を知り、経済援助として作庭させたのではないかと思います。
以上は推測ですが、肯定する根拠の一つとして、本格的な滝の存在が挙げられます。
現在の地形からは滝より好位置にある水源が近傍にはありませんので、もし大正期に滝の風情を作るとなれば、枯山水的な手法を用いて、それなりの風景を醸し出したのではないかと思います。
光安の時代には舘町が存在しませんので、地形的には西方から、開水路で水を引き込むことは十分可能でした。
つまり江戸時代の舘町出現以前でなければ、本格的な滝を造る発想は生まれなかったと考えられるからです。
なお大正の作庭時に、数百m離れた位置に滝より10mほど高位の水源があったことから、それを管径7糎の鉄管で導水しようとしました。
しかし道路の横断などのため管の屈曲が多く、特に縦断勾配が凹状となっている事からその部分に次第に砂泥が沈降堆積し短期間で管は閉塞したと推定できます。
おそらく滝の素晴らしさを目前にした先祖は、専門家の懸念を押し切り、ダメもとで、配管を試みたと思います。
なお現在の建物の北側には、江戸時代からあった池の半分と松の古木が残存し前代の風情を、僅かながら今に伝えております。(写真後出)
先祖代々見慣れた池を半壊するには、明治大正期の先祖には、かなりの葛藤があったはずで、それでも半壊に踏み切ったのは、遺構の事前調査で、旧池よりも新池がはるかに素晴らしいものになることを誰もが納得したからに他ならないと推測しております。なお現在の滝への通水は舘町通りに沿って流下している水路からポンプアップによるものです。
(5)大井光安の死について
Q:「続群書類従」の「矢島十二頭記」には、光安の死については天正16年打ち取られ節と文禄元年自害説の異なる二様の事が、二本立てで併記されています、どちらが事実でしょうか。
A:「矢島十二頭記」には次の事が記されています。
①説:天正16年霜月下旬より、仁賀保氏を中核とする由利十一頭に攻められ、子吉川右岸新荘館に拠り戦うが、ひと月ほど持ちこたえるが遂に落城し、五郎光安は妻の実家のある西馬音内に落ち行く途中で打ち取られる、時天正16年極月28日。
②説:天正20年7月仁賀保氏を中核とする由利十一頭に攻められ、荒倉館にこもり戦うも敗れ、西馬音内の妻の実家・小野寺茂道に身を寄せるが、同年(文禄に改元)極月28日、五郎光安は小野寺本家・義道から謀反の嫌疑を受け、岳父の苦衷を察し自害。
①説を西暦で読み替えますと、霜月下旬は今の暦で1月上旬から中旬に相当し、極月28日は新暦2月13日です。
このひと月余は氷点下の気温の続く厳冬期で、かつ積雪高が2mになんなんとする時期です。
どの様に考えても合戦ができる状況にはなく、したがってこの①説は荒唐無稽と断定されます。
この説を記した人物は、豪雪の容易ならざる事を、夢想だにできない関東以南に住していたと思われます。
もし①説を後世への歴史資料として作成したのであれば、それは初歩的かつ基本的な過誤である事を指摘しておきたいと思います。
しかし、境界紛争の際の裁判資料として寺社奉行等への提出目的で作成したのであれば、それなりの事実が含まれており有用です。
「群書類従」の編纂過程で、塙保己一のもとには、奉行所等からかなりの量の裁判記録が問供されていますので、一言記しました。
一方②説を記した公文書としては、明治13年12月、秋田県令石田英吉に提出された「羽後国由利郡誌の付録」があります。(秋田県立図書館、秋田県公文書館蔵)
明治新政府の命によって数年がかりで作成されたものであり、正確を期したものです。
この中には矢島を領した人名家名が記されていますが、「光安、文禄元年7月、仁賀保氏に敗れ以後矢島は仁賀保氏が領する。」と記載されており、②説を裏付けています。
ところで「続群書類従」の刊本が世に出たのは、明治後半から大正期ですから、提出公文書はその影響を全く受けていなかったと言えます。にも拘わらず、②説とは完全に一致していますので、資料からの検証でも①説すなわち光安討ち取られ説は否定されます。
一方私文書としては、生駒藩で代々家老職を務めた金子家の家譜があります。
これにも光安死期が文禄とあり、また十一頭との戦端が6月7日と記されていますので、内容的にも一致しており、②説を肯定しています。
従って、矢島、西馬音内に古くから伝承されている「光安、西馬音内自害」が事実と断定してよいでしょう。 (平成15年11月10日了)
2 矢島初代 生駒高俊公について
《矢島初代・生駒高俊暗愚説を検証する》
大井 益二
はじめに
矢島初代・生駒高俊について書かれたものは多数今日に伝わっているが、
一言で言うとすれば「暗愚の藩主・生駒高俊」となる。
しかしこの高俊評の発祥は宝永期と天保期に生駒藩により作成された文書2冊に収斂する。
本稿は何故に先祖誹謗が行われたか、否行われなければならなかったかを明らかにするとともに、讃岐高松より出羽矢島への改易の理由について再検討し、高俊の人物像についても検証するものである。
§1.高松城と幕府の外様大名対策について
高松城は讃岐初代・生駒親正が天正19(1591)年築城したもので、築城に際しレイアウトを担当した藤堂高虎は「ここは稀に見る天然の要害だ」と評したと言う。
城は3重の堀を備え、その堀のすべてに海水を引く堅牢なものである。
関が原の役後、徳川家康は、近畿、尾張、東海を領していた豊臣恩顧の大名の多くを中国、四国および九州に転封する。
このことは瀬戸内を扼する位置にある高松城の軍事上の機能すなわち増大した西国大名の東進を阻止する役割等が格段に大きくなったことを意味する。
その先駆として幕府は元和4(1618)年、高松と一衣帯水の小豆島を伏見奉行の管轄下においている。
家康の胸中には広島城主福島正則対策として、対岸の今治築城構想と並行して高松城を直轄支配する構想も描かれていたことは確かであろう。
東軍に組した大名の大半が、役の数年以内に加増の上転封されているのに対し、生駒家は父親正が西軍についたにもかかわらず、改易あるいは転封が猶予されている。
その理由として考えられることは「高松城は外様対策として、最重要拠点であり、その城主は家康直系の者を充てる」であったと思われ、家康は「親藩を担える人材が育つまで待ったとおもわれる。
しかし彼は生駒改易の布石を着実に打っている。
先ず三代正俊の正室として、幕府の信頼厚い藤堂高虎の養女(円智院矢島没)を嫁がせ、次に家康没後ではあるが、その嫡子4代高俊の正室として寛永10年、老中土井利勝の女を送り込んでいる。
これら両家との姻戚関係は一見生駒家の安泰にとってプラスとも考えられるが、逆に藩の内情が筒抜けとなり、また干渉を受けやすい状態でもある。
この様な状況は寛永17(1640)年の‘生駒騒動’の直前まで続き、その責により生駒家は出羽矢島1万石に改易される。島原の乱鎮定の翌々年のことである。
そして東讃岐は生駒氏改易の翌々年予定通り徳川光圀の兄・松平頼重を迎え、高松城とともに明治維新まで存続する。
‘予定通り’とする理由は、頼重の大名としての最初の赴任地が寛永16年の常陸下館であるが、その期間がわずか2年余であり、さらに在城は当初の2ヶ月のみであるところから、その領有は名目であると考えられるからである。
この様な経過を踏むのは、17歳の頼重に‘箔と帝王学’を付けさせ、大藩の領有の不自然さを薄めるとともに、生駒改易の本当の目的が‘難攻不落の海城・高松城に親藩大名を配置する’ことであることが、世間とりわけ生駒遺臣の目にあからさまに映らないようにし、事後の領国経営がスムースに運ぶことを意図したものであろう。
なお御三家が確立したのは元和5(1619)年であり、親藩を担いうる人材の絶対数が不足な時代であり、本来であれば長子の頼重が水戸徳川家を継ぐ位置にあったはずであるが、幕府としては高松城直轄を優先させなければならない事情であったことから、弟の光圀をやむなく二代目としたものであろう。
その後、頼重光圀兄弟はそれぞれの嗣子を交換し、頼重の系統が水戸徳川家、光圀の系統が高松松平家を継承し‘たすきがけ’を解消している。
この一連の経緯は、幕府が高松城をいかに重視していたかを物語るものであろう。
§2.通説・生駒騒動の出処について
いわゆる‘生駒騒動’は、通説によれば「新旧家臣団の抗争が、藩主・生駒高俊の器量不足から表面化し、その裁定が幕府に持ち込まれ、その結果‘藩内監督不行き届き’の責を咎められ、讃岐17万石を召し上げられ、出羽矢島1万石に改易されたとなっている。
この通説を記した文書は宝永年間に藩公認の上で作成され、京での生駒家菩提寺・妙心寺塔頭玉竜院が所蔵している「生駒記」と、これより120年後の天保4年、矢島九代藩主生駒親孝自らの著作である「讃羽綴遺禄」がある。
これら二書の内容は濃淡はあるが、改易まではほぼ同様で生駒家の由緒に始まり、讃岐四代の事績を記しているが、前者が騒動に重点を置いているのにたいし、後者は生駒家の出自および代々の先祖の武勲にもかなりのスペースを割き、騒動の経過および登場人物の出自についても丁寧な説明がなされ、客観性を装う筆致でまとめられている。
内容で特筆されることとして、初代親正から三代正俊については二書とも穏当な表現となっているが、四代高俊に至っては、幕府大老・土井利勝の口吻を借りる形式で酷評が続き、極め付きは「女童同然」の表現で締めくくっている事である。
この様な先祖誹謗が藩中枢の意思で作成され、そしてこれ見よがしに公的な箇所に置かれてい理由は、幕府巡検使等が京あるいは矢島に来た時、さりげなく閲覧に供し「当家が讃岐高松より出羽矢島に改易されたのは、ひとえに藩主高俊が暗愚であったためで、本来ならば生駒家は絶家となるべきところ、ありがたくも堪忍して頂き、その上1万石を賜ったのは、徳川様の恩情のおかげです」と伝えていることに他ならない。
これと同様なこととして尾張藩主徳川家の7代藩主・宗春の事例を挙げることができる。
「生駒記」が作成された宝永年間より年代は少し下るが、八代将軍吉宗の質素倹約を旨とする「享保の改革」が鋭意遂行中の頃、尾張藩において宗春はその政策に異を唱え種々の規制を緩和する等、真っ向から吉宗と対立した。
この宗春の所業に対し、吉宗は宗春を永蟄居に処し終生幽閉を命じた。
尾張藩は「幕府の命令は正しく、当家の宗春が誤っておりました」との事を具体的に示すため、宗春死後その墓石を金網で覆う、前代未聞の迎合策を講じた。
その金網が外されたのは百数十年が過ぎた明治になってのことである。
儒教が尊ばれた江戸時代ではあるが、藩存続を図るためには尊崇しなければならない先祖といえども徹底的に暗愚扱いとし、幕府の意を損じないことを最優先としなければならない時代であったことが分かる。
以上の背景から二書に描かれている「高俊像」は、正鵠を得ているかどうかは判別不能であり、従って‘生駒騒動’の経緯や登場人物の果たした役割についても再検討を要することになる。
§3.藤堂高虎の役割について
高俊の外祖父である藤堂高虎は、本領の津藩のほかに幕府の命で、息女の輿入れ先である会津藩蒲生家と加藤清正死後の熊本藩の執政を務め、生駒藩を加え都合160万石余りを統治した時期もあった。
これらの大名は、高虎嫡子高次の代に至るまでに、ことごとく改易されている。
高虎は家康の意向をハイレベルで理解できる人物であり、外様大名でありながら譜代大名格「別格譜代」)として重用されている。
藤堂家の生駒家への関与の象徴的な人物として西島八兵衛がいるが、彼は満濃池、瀬丸池等を始め90あまりの大池を築造し、さらに香東川の付け替えや新田干拓も行なっている。
これらの事業実施に当たっては莫大な費用を要したはずであるが、その出処を示す資料は不明である。
これらの事業開始の直前の寛永3(1626)年には領民の多数が餓死する未曾有の旱魃に見舞われていることから、生駒藩の財政は逼迫していたはずで、事業資金のかなりの部分は藤堂藩を通じてのものではないかと推量される。
しかし藤堂藩とても慈善事業をするはずもないと思われ、結局のところ後年讃岐国を領有する手はずである幕府が資金提供者であると考えてよいであろう。
さらに高俊の岳父土井利勝が幕閣首座であるところから、その出資についても、閣内の多くは「よくある縁故融資」と思ったであろうが、それが将来旱魃対策がなされた東讃岐一国が親藩領とする布石であることに思い至った人物はごく限られていたと思われるが、その中に高虎高次父子がいたことは言うまでもないであろう。
藤堂藩の常識を超えた高松藩への貢献は、生駒家に対するものではなく、徳川家への忠勤であることには疑問の余地がない。
§4.土井利勝について
高俊個人の属性を記している文書は玉竜院所蔵の「生駒記」と生駒家九代親孝著述の「讃羽綴遺録」の二書に集約されることは既に述べた。
これら二書とも「高俊暗愚説」を裏付ける記載は、ほぼ同様であるので、ここでは今日引用されることが多い「讃羽綴遺録」(以後綴遺録という)を俎上とする。
この中の高俊の行状を考える上で岳父の土井利勝との関係は重要である。
老中首座の女を正室にしていることは、高俊がいたらず多少の問題を起こしたとしても大事に至る前に消し止めることが可能な環境にあったとも考えられる。
しかし利勝が生駒家改易の布石として女を娶わせたとすれば、もはや絶望的である。
先ず虚弱な女を正室にすれば、嗣子はできにくいであろうし、「三年子無きは去れ」を実行するにしても憚りがあり、仮に離縁に成功してもその後の再婚にも幕府の許可が必要となり、そこには旧岳父が控えているのである。
生駒家内部では婚儀から程なく、このことに気づいたはずで、このままでは当主高俊の身に変事が生じた場合、嗣子無きによりお家断絶となることを危惧したであろうことは容易に察せられる。
この打開策として考えられるのは、不治の病気療養のため家督を一門の者に譲り自らは正室もろとも引退する案であろう。
だが正室の輿入れには少なからずの土井家の付け人が送り込まれており、仮病を装ってもとき経ずして利勝のもとに虚偽であることが報告される
次なる策として公然と奇矯な振る舞いをし、精神異常を喧伝し、それ故を以って「藩主交代」を願い出る事も考えられる。
奇矯な振る舞いとして綴遺録には、美少年を集め「生駒踊り」なるものに熱中したとあり、また男色を好み結婚4、5年を経ても子供ができないことが記されている。
これらのことが取りざたされていた寛永15年、正室は輿入れ後わずか5年足らずで死没しているが、綴遺録には岳父のコメントは記されていない。
生駒家内部では表面的には悲しんだであろうが、内心では安堵したであろう。
逆に利勝はカードを失ったことになり、代案として、高虎の継嗣の藤堂高次を通じ、猛然と生駒藩内部に介入し、影響下にあった前野、石崎らに策を与え、とにもかくにも内紛を幕府に持ち込ませることを策している。
この期におよび高俊はじめ生駒一門は、幕府の狙いが‘高松城略取’であることを悟り、「もはや転封は免れ難い」と観念し、一門の生存、家名を残すことに、高次の助言を入れ方針を転換し、捲土重来に一縷の望みを託したと推量される。
なお徳川実紀には高俊長子として「高法」の名が記されているが、生駒家譜には記されておらず、実在したかどうかは不明である。利勝が女が「不生女」であることを知られたくないので実紀に記させたのではないかと筆者は考えている。
§5.生駒家と藤堂家のその後の関係について
綴遺録には高俊と高次との関係を示すものとして「伯父甥の縁を切る」があるが、生駒家の公式記録である「御納戸日記」に最も多く記されている大名家は藤堂家である。
年始の挨拶に始まり、種々の年中行事はもちろん、事あるごとに両家は交流しているし、天保の大飢饉時には藤堂家より国許矢島に米500俵が送られている。
改易より二百年ほど経た頃のことであり、生駒家に対する単なる‘後ろめたさ’からではないことは明らかである。
おそらく生駒家が幕府の意を受け入れずにひと波乱を引き起こした場合には、藤堂藩とても執政責任を問われ、ただでは済まなかったはずで、高俊の大局的な措置に対し、高次はそれを多大な恩義とし、「藤堂藩が続く限り生駒家の恩義を忘れるべからず」と次代の藩主に申し渡したと考えざるを得ない。
なおこの親密な状況は江戸期を通じて変わることはなかった。
§6.高俊の人物像について
綴遺録には高俊に実子ができない理由として、「男色故に子供ができない」とあるが、矢島入部後には、地元有力者の女との間に五男三女が生じている。(生駒家譜)
さらに高松時代の子と思われる者が成人後に、伊勢藤堂家に立ち寄った後矢島に来たとの文書も散見される。
これらの事実から高俊は男色にかまけ、嗣子誕生に関心が無いとの綴遺録の評は全く当たっていない。
また徳川実紀に島原の乱の直前即ちは寛永14年5月に、将軍家光の前で余興として狂言を演じていることから、彼は能狂言への造詣が相当に深いことがわかるし、さらに梅津政影日記には秋田藩主佐竹義宣の茶会に高次と共に招かれている等から、水準以上の教養人であったと思われ、少なくとも日常行動から‘暗愚’の評が発生する人物ではないことは確かである。
もし綴遺録にあるような‘生駒踊り’の様な奇矯な行動が事実とすれば、それは美少年らの振り付けを含めすべて自作自演の狂言である可能性が高いし、そうであるならば彼は企画力に富んだ人物であったと思われる。
矢島入部後の高俊の治政を挙げると
・言語をはじめ風俗慣習が全く異なる讃岐衆と在地武士団との融和を図り成功している事
・直接日本海に通じている領地を手放してまでも、隣藩との換地を行い領国経営の合理化を優先するとともに、境界を確定し将来のトラブルを未然に防止した事
・矢島でもうけた子らを将軍に謁見させ、家の存続を早期に実現している事。
・嗣子以外の子女を名のある家に出し、中には加賀前田藩に二千石で仕官させ大大名との交誼にも意を払っていること。
以上の事項を総括すれば、例え小禄であってもその経営を他者に任すことなく、あくまで生駒家自身により行いうるよう、その基礎造りに渾身の力を振り絞ったといえよう。
生駒家とほぼ同様な経過そして改易地も同じ酒井藩の管轄下であった加藤清正嫡子の忠広は、やはり堪忍料1万石を与えられたが、自ら経営することはなく、彼の代で加藤家は消滅しており、対象的な結果となっている。
以上述べてきたように、高俊暗愚説の根拠は皆無といってよく、逆に地味ながら明君を想わせる事実は少なくない。
戊辰の役では生駒藩は反徳川軍となり城下を譜代酒井藩に焼き払われるも、官軍の一部隊として秋田県各地に転戦し、その功により、五千石ほど加増された後に廃藩置県を迎える。
生駒家の菩提寺は東京都台東区の海禅寺(臨済宗)であるが、高俊の墓所のみが旧矢島町の竜源寺(曹洞宗)である。
海禅寺の墓所はさきの大戦の空襲により本堂もろとも灰燼に帰したが、昭和54年第22代生駒道孝氏により再建立され、高俊は先祖子孫と共に合同慰霊されている。
もし高俊が通説のような暗愚の藩主であったとすれば、果たして生駒家はこの日を迎えることができたであろうか疑問である。
なお暗愚説の根拠のもう一つとして「七条左京の遺児4人を殺害」があるが、この事件は‘造られた伝承’であり、左京の遺児らは、水野四郎衛門帰国のおり讃岐に同道している。(姉崎岩蔵・生駒藩史)
この事から伝承の作成意図は、暗愚説を補強することにあったと思える。
§7.矢島における高俊について
矢島入部後の高俊の室として、今氏と‘某氏’の二人が生駒家譜に記されている。
前者は矢島領の日本海への出口である塩越(旧象潟町)の有力者の息女であり、後者の「某氏の女」とは矢島の有力勢力の息女である。
それぞれに複数の子があり、今氏の系統はその後の矢島藩主に続き、某氏の系統は男子は加賀藩に移籍し女子は他家に嫁している。
この地方の女性を「稀なる美人なれば云々」と評している古文書があり、おそらく高俊夫人そして娘も際立った美形であったと想定され、高俊の周辺は華やいだ空気が漂っていたことは、今日の女性の風貌からもうなずけるものである。
このように高俊は家族に恵まれており、高松時代に比べて、充実した家庭生活であったといえよう。
そして由利地方は番楽等の芸能が今日でも盛んであり、その分野に長じている高俊にとっては自ら演ずる等、趣味生活も豊かであったかもしれない。ちなみに彼の大叔母・大塚万千代は秀吉時代に諸大名が綺羅星の如く居並ぶ前で、歌舞音曲を披露している才人である。(高松初代・生駒親正書状、筆者蔵
また彼の起居する八森上城(陣屋は秀峰鳥海の麓であり、眼下には清流子吉川が豊かに流れている。
この恵まれた自然の中で、軍事訓練をかねての熊猟、鮎鮭漁などを満喫したであろう。
晩年の彼の胸中は多少の後ろめたさはあるものの「出羽矢島に配されたのは幸運であった」とのおもいに満たされていたのではなかろうか。
あとがき
讃岐生駒藩の出羽矢島への改易は、ひとえに高松城の立地の稀少性および軍事機能の優秀性の故に為されたことは、時を経ずして御三家に次ぐ親藩大名が配されていることで明らかであり、何人であっても転封は不可避であったと断定してよいであろう。
従って後に語られる改易理由の数々は幕府裁定を正当化する作文に過ぎないものである。
一方、矢島転封時は未だ徳川幕府は草創期であり、天下の擾乱に乗じて再び中原に躍りでる可能性はゼロではない時世であり、11年後の由比正雪首謀の「慶安の変」がこのことを物語っている。
従って、武力を持つことは、なお重要な時代でもあった。
高俊の矢島下向中の胸中には「いずれ再び」の思いがあったであろうし、敢えてそう自らに言い聞かせていたかも知れない。
そうでなければ讃岐より付き従って来た200人余の家来たちに申し訳が立たないとも考えたであろう。
将軍の前で狂言を演ずる彼であれば、その性格は闊達であったと思われ、雪深い矢島に来ても、希望を捨てず家来にも土着の民にも明るく振舞っていたと思える。
地味ながら矢島初代藩主は明君ではないかと筆者は考えている。
ところで八森城址に御座す矢島神社には、讃岐初代親正公、矢島末代の藩主親敬公のみが祀られているが、今日の矢島の基を造った高俊公は祀られていない。
たぶん綴遺録の存在が災いしたと思うが、その内容は全く根拠のないことは述べてきた通りである。
よって高俊公が合祀されんことを衷心より願って稿を終える。
最後に本稿の掲載をかなえてくれた矢島町郷土史研究会そして高松市歴史民俗協会に深甚の謝意を表し、合わせて姉妹都市である高松市と由利本荘市の相互理解に僅かにも資すことができれば、望外の幸せである。
(平成24年3月30日了)
3 由利十二頭大井光安と息女鶴姫そしてその子孫について
由利十二頭大井光安息女・鶴姫とその子孫について
大井 益二
§1.はじめに
由利十二頭矢島満安(大井光安)の息女・鶴姫について記された二次文書等は多数今日に伝えられている。
その主なものとして『奥羽永慶軍記』、『続群書類従・矢島十二頭記』が挙げられることが多いが、記述年が慶長年間の鶴姫4歳から14歳までのものがほとんどで、没年に至る晩年の状況に触れたものはきわめて少ない。
特に関ケ原後に由利を統治した楯岡氏および讃岐より転封の生駒家との関係等については僅かの記載しかない。
さらにその子孫となると、曖昧模糊と言ってよい。
幸い平成に入り刊行あるいは公的機関に寄託された史料として、「矢島大井氏履歴文書」、「飯塚家文書」、さらに鶴姫の子が記載されている「前橋・酒井家文書」および舘岡豊前守家譜などがあり。
本稿はこれら史料の作成された背景およびその内容について検討し、鶴姫と舘岡氏および生駒氏とのかかわりについて考察したものである。
§2.矢島大井氏履歴文書について
標記文書は大井俊郎家(東京都新宿区)が、伝承してきたものであり。
同家は戦国時代の末期まで赤宇津郷(由利本荘市亀田町付近)の蛇田に在住していた信濃源氏・小笠原氏系の一族であり、赤宇津あるいは赤穂津さらに小助川と称していた。
由利十二頭の一方の雄であったが、関ヶ原戦以後は新領主最上氏に帰属した一派と、佐竹藩家老・梅津氏に帰属した二派に分かれている。
前者の赤宇津孫次郎は、最上氏改易後は、いわゆる“最上衆”として越前松平家に預かり身分(のち下級家臣)として、明治維新まで存続し、一族の中から三岡八郎(のちの由利公正)を輩出している。
しかし佐竹藩の家老・梅津憲忠家の家裁として江戸時代を過ごした大井俊郎家がどのような経緯で、佐竹の陪臣となったかは、同氏の綿密な調査にも関わらず未だ判然とはしていない。
なお由利公正旧姓である“三岡”は、長野県佐久地方の地名であり、JR小海線の駅名でもある。
このことから赤宇津孫次郎は、自身の遠祖が、由利以前は佐久三岡に在住していた事を知っていたことになる。
また松平家臣となった孫次郎は一時期、「大井孫次郎」とも名乗っている。
従って明治維新の折、公正氏の改姓の候補として古い順に記すと大井、三岡、由利そして赤宇津と四通りあった事になる。
ところで標記文書は今から280年前の享保の頃に、同家先祖に矢島方面よりもたらされたものである。
具体的には、当時の矢島藩家老で、大井俊郎家先祖と遠縁である小助川治左衛門光隆と考えられる。
以下に全文を示す。
《矢島大井家履歴文書》 作者:生駒藩家老職(小助川光隆) 所蔵者:大井光弘(大井俊郎氏祖)
濃州高倉 住館。源姓木曾四郎義宗の末葉。
大井五郎丸義久、応安元年戌申の年(1368)、羽州矢島に下向す。
義久の嫡子太郎の子大膳大夫義満、その子五郎大夫光安後、大江満安と改む一族といい。
光継を救うの刻、小笠原重挙数度戦う。
その子、十二党をかたって、終に満安を攻め、文禄元年七月二から十八日、羽州矢島荒蔵城落城す。
同年十二月二十八日、仙北西馬音内の館にて死す。
妻は小野寺肥前守茂道女、満安嫡男太郎、次男亀丸三女鶴女という。
のち叔父与兵衛尉、迷心して二人の男自害。
鶴女を百姓に託して菊池五郎兵衛某もらい受け養う。
また東禅寺右馬頭某養女となり、仁賀保小笠原兵庫殿嫡男・蔵人主室となる。
寛永八年辛亥尼となり、妙月とあらたむ。
後年、羽州庄内賀茂の光安寺を建てる。
妙月、矢島の矢ノ又の寶鐘院を建てる。
慶安四年(1651年)三月二日卒。
矢島の主生駒高俊、米二十俵を寄付し、今において矢島の主、これを給うという。
この文書の作成目的であるが、当時幕府は小笠原貞任なる浪人の素性を調査している。
享保十二年、貞任は「わが先祖は文禄2年に小笠原諸島を発見した」ことを根拠に、同島への渡航と領有権を町奉行・大岡忠相に願い出ていたからである。
享保20年、取り調べの後に貞任は罪に問われ、財産没収と重追放に処せられている。
このような経緯から享保12年から貞任の出自調査とりわけ小笠原系(大井姓を含む)について全国調査がなされている。
生駒藩にも下達があり、大井家は商家ではあるが、由利十二頭の裔との風評があるところから、調査対象となり、藩より同家に対し、由緒書等の提出を求められた事に対する回答文である。
なお「回答文」と断定した根拠は、大井光弘家と佐竹藩とのやり取りであるので、そちらを参照願いたい。(後出)。
ところで、生駒藩および大井家は面倒なことにならぬよう、作成には細心の注意を払っている。
具体的には本文の冒頭で「濃州高倉住館。源姓木曾四郎義宗の末葉。」とあり、佐久そして小笠原との因縁には触れていない。
また鶴姫が大井光安の娘であることは周知されていたと見え、その後裔の存在をさりげなく記すことで、本文が家伝であることを、言外に伝えている。
これに対し同様な立場にあった大井俊郎家先祖と佐竹藩とのやり取りを以下に示す。
大井家には、享保12年丁末の夏、佐竹藩士・川崎嘉右衛門より大井家の由緒書の提出を求められ、同家の当主・大井光廣が系図から、佐久時代の四代を含む由緒書を提出した。
その中には大阪冬の陣で激戦となった今福の戦いで佐竹藩家老・梅津憲忠の従者として奮戦した大井光基の名も記載がある。
ところが日ならずして、佐竹藩より「佐久、小笠原、大井光基奮戦」などの記述を削除する旨の指示があった。
要するに“小笠原”とは無縁の家系であることが分かればよい文面としたのである。
同家にとって極めて心外であった事が伝えられており、この時より二十年後に作成された分家の系図には、当然のこととして、小笠原そして今福の奮戦が記されている。
以上が佐竹家陪臣であった大井光弘家提出文書の経緯である。
大井光弘が矢島大井家履歴文書を必要としたのは、藩の説明だけでは、その意図が計りかねたからであろう。
先祖詐称の調査であるので、回答文に誤りがあれば、場合によっては幕府から「同罪」との咎めも受けかねない事も危惧したであろう。
そんなことから、共に由利十二頭であった好で、矢島大井家の対応をぜひ知りたいと思ったことであろう。
なおこれらの幕府調査の結論は、大藩である豊前小笠原藩が「小笠原貞任なる人物は当藩とは無縁」との回答を以て終了している。
なお幕府への提出文書を作成するに当たり、生駒家は江戸在府の家臣を動員し情報を集め、その意図を把握したはずで、これに対し大井光弘家は、遠隔地でもあり、情報は乏しかったものであろう。
以上当文書の作成背景について考察したが、記載内容には興味ある事項が含まれている。
特に最後の一行「矢島の主生駒高俊、米二十俵を寄付し、今において矢島の主、これを給うという」は、生駒家と矢島大井氏との関係を具体的に記したもので、注目に値する。
また高俊の、讃岐より矢島への国替えは、寛永十七年であるので、鶴姫の晩年の十年間が、両者が相対した期間となる。
§3飯塚家文書について
標記文書は西馬音内・飯塚家に伝承されてきた文書であり、同家はは小野寺氏入部以前より同地方に居住していた旧家である。
文書は横手市史資料編に収録されており、以下引用する。
なお長文となるので、一部省略している。
《飯塚家文書*》 作者:小野寺茂道子孫 要請者:戸部正直(奥羽永慶軍著者)
-前略-
・其の子茂道小野寺孫三郎、妾腹ノ故、西馬音内ニ託ス。後肥前守ト号ス。(大井光安岳父)
・其の弟義道小野寺孫十郎、横手ノ本城ニ住ス。秀吉公高麗御陣ノ時、遠江守ト受領ス。
・其の弟康道小野寺孫五郎、大森二居城ス。
・女子(茂道の娘、鶴姫の生母) 由利矢島ノ城主大江五郎満安ガ妻。
・其ノ弟 孫六郎 慶長五年ニ死去ス。
・其ノ妹 最上義光ノ臣・土肥半左衛門ガ妻トナリ、一女ヲ生ム。
・其ノ弟 八之丞小野寺佐渡守、のち式部大輔ト号ス。父肥前守茂道同道ニテ庄内ニ走リ、光安寺ト云ウ寺ニ故アリテ逗留シ、ソノ後戸沢右京ガ元ニ走リ寛文三年ニ死去ス。
※ さらに矢島光安の長女で小野寺茂道の外孫である鶴姫の項には、その消息に加えて矢島落城にかかわる事項が以下のように詳述されている。
・女子於鶴(おつる)
満安ガ弟ニ与惣兵衛ト云ウ者有リ。
此者、異心ニヨリテ仁賀保安審ニ矢島ノ城ヲ奪ワレ、拠ナク西馬音内ヲ頼ミ矢城ヲ取り返ント謀りシニ、反テ横手義道暗弱ニシテ満安ヲ殺ス。
矢島落城ノ時、此ノ女子(鶴姫)僅三、四歳成りシヲ、百性密二隠シ育ヒシヲ、智リ、庄内ノ菊池五郎兵衛ト云う者乞受ケシヲ、又東禅寺右馬頭、菊池ガ手ヨリ乞受養シガ、誠ニ稀ナル美人ナレバ、仁賀保兵庫頭子息・蔵主ノ奥ニ貰レ、去リ乍ラ、子共ナシ、其後寛永八年禿レラレ、奥方於鶴殿ヲ満安ノ古老臣、矢島へ迎ヒ奉り、君臣ノ礼ヲ厚ク養シト也、寛文四年矢島宝鏡院ト云山伏ノ所ニ死去シ賜フ。
法名妙日ト号ス。
文書の作成者は奥羽の関ヶ原戦と言われている「慶長出羽合戦」で長男二男を失い、三男を連れ、庄内に走った西馬音内城主小野寺茂道の系統の人物であることは、記載内容から考えて確かといってよい。
この文書には鶴姫の血縁者が網羅されており、さらに仁賀保蔵人との関係や亡父の供養のため建立した光安寺についても記されている。(『横手市史 資料編 古代中世 P674~P675』)
ところで飯塚家文書が庄内方面から西馬音内の旧家飯塚家に渡った事情について考えてみたい。
文書の記載の主体が西馬音内領主・小野寺茂道の子孫であり、特に鶴姫については詳述されている。
この事から文書作成者の意図は、鶴姫の生涯を記述することにあったことは明白で、庄内地方に伝わる知見のみではなく、由利方面からの情報も集めている。
そして作成姿勢は、作者自身の子孫等に伝える資料として作成されたものではなく、「妾腹、旅宿腹、暗弱にして、美人なれば」などの、体裁を整えようとした形跡がないことから、親しい知人からの要請に応えたものの可能性が濃厚である。
親しい知人とは西馬音内の旧家の飯塚家当主であることは自明であるが、同家に関わる情報が文書の中に全くないことから、飯塚家を介して情報授受を要請した人物が、他に存在したことは確かである。
文書中の最期年が寛文4年であるので、これ以降で矢島大井氏系統の人物情報を収集していたのは、『奥羽永慶軍記』(以下『永慶軍記』という)の著作者で、西馬音内へは半日の行程にある横堀村の医師である戸部正直と考えてもよいであろう。
『永慶軍記』(上梓元禄11年)との間には、矢島方面からの伝聞情報以外には、内容には若干の矛盾はあるが、大筋においてほぼ同様といってよい。
また「義道暗弱にして光安を殺す」とのやや感情的な表現もあるが、「巻二十六 矢島五郎最期の事」の中には、「扨も小野寺遠江守義道智謀なき故、敵の計略に乗て、今年罪なき矢島を討ち」とさりげなくかつ巧みにその意を、戸部は取り入れている。
この飯塚家文書と矢島大井家履歴文書の相違点を見ると、鶴姫死去年、妙月が妙日、寶鐘院が宝鏡院、そして光安寺の創建時期等の移動があるが、この事は逆に両文書が独立したもので、互いに干渉した形跡がなかった事を示している。
鶴姫にかかわる事項で大きな相違点は、死亡年が「慶安四年(1651)三月二日」であるのに対し飯塚家文書では「寛文四年(1664)」と、13年の開きになっている事である。
たとえ矢島方面からの情報としても、死亡年がこれほど異なることは考えにくく、おそらく鶴姫の身近な人物の死亡年が誤って記されたと考えられる。
親兄弟は既に死んでおり、後述するように、男子は前橋に強制移住になっており、身近に存在しているのは娘のみとなる。
さらに付記すると鶴姫が落飾し寛永8年は、夫婦に擬せられた仁賀保蔵人の死去年でもあり、幼少ゆえに“なさぬ仲”ではあったものの、鶴姫の胸中には複雑な思いがあったと思われる。
なお仁賀保家は関ケ原以後は日立に国替えとなったが、元和8年には再び由利を領しているので、両者はそれぞれの状況を知っていたと思われ、幼くして生き別れた姉、弟」との想いがあったのではないかと推量される。
なお「光安寺」の事実関係については、その存在の有無を含め今後の課題としたい。
§4.舘岡氏関係文書による由利系人物について
山形最上氏が由利地方を領したのは、関ケ原戦の3年後の慶長8年(1603)で、赴任したのは、重臣である楯岡豊前守満茂である。
当初は最上領の最北で、佐竹領と接する位置である亀田に本拠を置いている。
この地域は由利十二頭の一方の雄である赤宇津氏の所領であったが、最上藩は同氏を最上家臣団に組み込む事を条件にスムースに収容している。
その後、慶長十五年から領内経営の中核とすべく子吉川下流に築城を開始し、同十七年に、それまでの亀田を離れ、新城を拠点にしている。
城名は「本城城」と命名されたが、後六郷氏の居城の際本荘城と改名されている。
城主楯岡豊前守は広く複雑な地形である由利を統治するため、弟楯岡長門守満廣を要衝の地である矢島に配している。
この長門守の室に鶴姫がなるのであるが、その事を記した一次史料は由利地方には現在のところ見当たらない。
そして最上氏がお家騒動を咎められ元和八年(1622)改易された事に伴い、その家臣団も徳川家の親藩および譜代の大名家に配流されている。
その中にあって、舘岡一族は前橋藩主酒井藩に預けられるが、舘岡豊前守満茂は同藩に随臣し、その子孫は今日に至っている。
このような経過から、楯岡一族のその後が判明している。
同家の系図には豊前守には男子がなかったので、息女に弟長門守の嫡男親茂を迎え後嗣としたとあり、その親茂は若くして死去したので、やむなく長門守の息女に寺内遠江守の子信義を迎えて後継としたと記されている。
従って、矢島に残った鶴姫の手元には何人かの娘がいた事となる。
また前橋から姫路に意封された酒井藩資料には「最上衆」として、次の人名が記されている。
《福井松平家文書》 調査者:大井俊郎氏
本城豊前、大山内膳、楯岡七郎右ェ門、宮崎六郎兵エ、武子助太夫、八森藤左ェ門、志賀次郎兵エ、滝沢八左ェ門、矢島九郎右ェ門、矢島門兵ェ。
文中、注目される事として、楯岡長門の名がないことと、由利系の三名即ち滝沢八左衛門、矢島九郎右衛門、矢島門兵衛の名があることである。
また八森藤左ェ門の名があるが、この人物は長門守の次弟との伝えがある。
系図の中に長門守の実子の名はありながら、その父の名がないのは不自然で、舘岡一族はお預けの身であり、この場合男子であればたとえ幼少であっても前橋行きから除外されることはなかったと考えられるので、名が無い事は、この時既に死亡していたと断定される。
また由利系の姓の者は楯岡兄弟と由利の女との間に生まれた実子であったと考えられ、その名は母系の姓を冠したものであろう。
なおその他の「最上衆」として秋田方面と関りがあった者として、老中土井利勝に預けられた鮭延秀綱がおり、越前松平家に預けられた赤宇津孫次郎もいる。
幕府の狙いは豊臣政権下での奥州仕置きの折に勃発した、葛西大崎一揆同様の再現を未然に防止するため、あらかじめ中核となるおそれのある一族を地元から抜き上げておく必要があったのであろう。
なお豊前守満茂は寛永六年、84歳の長命で没しており、墓は前橋市紅雲町一丁目、長昌寺にある。
なお説明が前後するが、鶴姫と舘岡長門守が夫婦であった事を示す文書は唯一「続群書類従」所集の矢島十二頭記」である。
この文書は元禄二年に、旗本仁賀保氏と矢島生駒氏との境界紛争の際、両家から公儀の評定所に提出されたもので、両書を合本し改めて両者に下げ渡されたものであると考えられる。
その事を裏付ける理由として、次の事項が挙げられる。
《矢島十二頭記が訴訟資料と考えられる理由》
①両藩から提出された文書が、ページを変える事なく続き書きされ、不離一体となっており、現代の契約書の割印と同様な効果を備えていること。
②同書の構成は、前段が仁賀保有利、後段が矢島有利な内容となっており、ほぼ同一内容の者が、前段が仁賀保領、後段文が矢島領から、複数後年発見されている。
双方とも作成した文書を寺社や旧家等にバラまき、状況証拠になることを期待したと考えられ、今日に伝わったものはその残滓であろう。
③群書類従」編集の際、町奉行より厖大な訴訟資料が、塙保己一主宰・和学講談所に譲渡されており、矢島十二頭記の冒頭にも「総検校 塙保己一修」と肩書が記されており、官から官へ移動したことは確かである。なお§2で述べた小笠原貞任の裁判記録も、南町奉行から塙保己一に譲渡されたものである事が明記されている。(温故叢誌第59号-温故学会)
ここで「矢島十二頭記」の由来に触れたのは、各所に存在している「由利十二頭記」の存在理由についての論究が見当たらないので、私見を付け加えさせていただいた。
本題に戻るが、鶴姫は文中「お藤の方」との名で登場するが、この名は兄舘岡豊前守の室の名で、その娘は有力者の遠田家(現大内町)に嫁しているとの伝えがあり、豊前守と遠田家との関係を示す客観的記録に登場していることから「お藤の方」の立場も確かであり、よって仁賀保家提出文の“お藤の方”は、明らかな誤りである。
鶴姫婚姻にかかわる部分を次に示す。
《矢島十二頭記》 所集:「続群書類従」 最初執筆者:旗本仁賀保家
九月七日晩西馬音内三衛門計にておふじ殿(鶴姫)仁賀保根城より、ぬすみとり、西馬音内、八森へ兵庫殿お帰りなされそうろうておふじ殿をご吟味なされそうらえどもなされ候。慶長九年、三月、矢嶋四十人の者ども、取り計らいにて、おふじ殿(鶴姫)をば楯岡長門守殿奥方に差し上げ候。」
本文を挿入した仁賀保家の目的は、生駒藩との紛争地点が仁賀保領であることをさりげなく、行間に散りばめる事が主眼であるが、そのことを補強するために、矢島衆すなわち生駒衆の行動に“盗む”などの下劣な表現を混在させ、評定担当者の心象に働きかけようとしたものであろう。
なお先に掲載した矢島大井家履歴文書」の文中に「小笠原重挙数度戦う」や「仁賀保小笠原兵庫殿嫡蔵人主室となる。」があるが、この小笠原を書き込む必要性はないと考えられるが、敢えて書き込んだ理由は「旗本仁賀保家も小笠原一族ですよ」と告げ口した事に他ならない。
つまり数十年前の境界紛争時の意趣返しを、生駒藩はさりげなく仁賀保家を揶揄したものと推量される。
この文面で重要な事は、仁賀保側の悪口そのものが事実と異なった場合、逆に仁賀保側の主張に疑義が生ずることになるわけであるから、鶴姫が長門守の妻となったことは事実と考えてよい事である。
また鶴姫が庄内賀茂に非業の死を遂げた父五郎光安の供養のために建立したと思われる「光安寺」を建てたと記されている。
寺院の建立およびその後の維持管理には経済力が必要であり、さらに最上氏領・庄内での開山であることを考え合わせると、楯岡氏の庇護が不可欠である。
この状況を可能なさしめる事態は「楯岡長門守内室・鶴姫」以外には存在しえないと考えられる。
そして「光安寺、」を建立することで、男子の身寄りがおらずとも、鶴姫が由利十二頭・大井光安の直系である事を周知させ、矢島大井の再興の布石としたのではないかと筆者は考えている。
なお評定の採決であるが、江戸より検視が下向し、調査の上、生駒家勝訴、仁賀保家敗訴で終着している。(矢島町古文書散歩第三集)
§5.生駒高俊と鶴姫系大井氏との関係について
藩の公式文書である生駒家譜に・四代正親時代(元禄15年宝永3年の3ヵ年半)の記録に「生駒家菩提寺・海禅寺(東京都浅草)御墓前、献灯篭記名」の項に、大井光長の名が、金子、小助川、高柳、佐藤、相庭、河内らの矢島満安股肱の臣の氏名に先立ち記されていた。
このことは大井光長が藩の重職として在籍していたことを示し、その背景として矢島光安の遺臣の後裔が、こぞって彼を押し上げていたことに他ならない。
この状況を現出する要因は、光長が光安の血を引いている事以外は考えにくい。
一方、生駒家としては讃岐家臣団と地元大井遺臣団との融和を図る必要から、むしろ積極的に推し進めた策であったと思える。
ところで、鎌倉初期の和田合戦のおり、実朝(三代将軍)を身をもって救った恩賞として、由利郡は源頼朝の側室信濃守小笠原遠光の息女・大弐局に与えられるが、実際の統治は既に佐久地方の地頭職であった甥にあたる大井朝光で、その後も朝光の嫡子太郎光長が領している。
朝光の“朝”は鎌倉将軍・頼朝の一字であり、光長の“長”は小笠原家代々の通字であり、由緒ある名であることがわかる。
そして実質的には由利初代と考えられる光長の名を、復活矢島大井氏の初代名としたわけであるが、その命名者は、大井光安の血を引く人物は唯一鶴姫であるところから、同人と考えるのが自然であろう。
では光長の母が鶴姫の娘であることは確かであるとしても、では父が誰であるのか考えてみたい。
最上氏改易後の矢島領主は十二頭でもあった打越氏であるが、嗣子不在となり7年ほどで断絶しており、鶴姫とのかかわりは伝えられていない。
その後は徳川四天王・堺市の預かり地となり8年後の寛永17年(1640年)讃岐より生駒氏が入部し、初代は生駒高俊となる。
生駒氏と鶴姫との関りを示す文書等はこれまで発見されなかったが、先に示した矢島大井家履歴文書の末尾に次の様に示されている。
「矢島の主生駒高俊、米二十俵を寄付し、今において矢島の主、これを給うという。
文書が書かれたのは享保年間であることから、生駒家から鶴姫系に米が支給された期間は少なくとも80年と長期に至っている。
両者の関係は最小限の支給物であるところから、常識的に考えると、“扶養家族”となるが、三世代にわたっていることから、密接な血縁関係にあったと考えてよいと思う。
つまり大井光長の母は鶴姫の娘、父は生駒高俊であると推量されるのである。
矢島在住の生駒家当主は初代高俊以後は八代親睦までないことから、血縁関係が生ずるのは高俊以外いないからである。
以上、光安以来ほぼ一世紀ぶりに、矢島に大井氏が復活したわけであるが、その後は士分としての大井氏は公式文書には全く登場しない。
そして入れ替わるように、商家大井が藩の手厚い保護のもと、城下に誕生している。
この経緯について記した文書等は伝わっていないが、大井光長は讃岐系および矢島系双方の家臣団が庇護している状況であり、この状況下で大井家改易させる力を有しているのは幕府以外には考えにくい。
具体的には、慶長出羽合戦で、大井光安の遺臣たちは小野寺氏の一部隊として、反徳川の上杉方に加担していたわけであるから、その子孫を公然と藩重職にした事はやはり“公儀を畏れぬ所業”と考えた人も、藩内外に少なくなかったとも思える。
碑に刻まれた文字を削り取ることも考えられたと思われるが、碑は浅草・海前禅寺であり、蜂須賀家、豊前小笠原家などの大名家や、旗本などの菩提寺であることから、かえって“悪目立ち”になることも考えたであろう。
「ではどうすべきか」種々提案があったであろうが、到達した結論としては国元矢島の武家大井家を生駒藩から削り取るのが最適との結論に至ったものと思う。
では非武家となった一族として、筆者が確認できるのは、矢島の商家大井家と山形県酒田市近郊の大井藤四郎家である。
藤四郎家の由緒書には、「元禄五年生まれの先祖について「矢島が生誕地であること、武士であったがやむなく浪人したこと」等が記されている。
一方、公式文書である生駒家譜の矢島初代高俊の子についての記載がある。
正室・お今の方との間には四名の子があり、矢島二代、三代藩主を輩出していう。
また側室の間にも四名の子があり、長男生駒正武は加賀前田家に、二千石の大身で移籍し、女子二名も格式ある家に嫁している。
そして側室の出自については“母は某氏の女”となっており、明らかにされていない。
仮に佐竹家や仁賀保家等のしかるべき名家から嫁して来たとすれば、実家の公文書にその旨が記される事から、受け入れ側の文書に“某氏の女”などの記載は許されないことである。
これまでの検討で、光長の母が鶴姫の娘であることは確実であるが、仮にその人物が、某氏は父系の氏名となるので“舘岡”となる。
しかし鶴姫夫・舘岡長門は既に死亡しており、また兄光繁は前橋酒井藩に随臣し氏名も本城氏に改正している。
従って、公式記録には“某氏”としか書きようがなかったものと考えられる。
敢えて氏名を称する次善の案として“大井”とすることも考えたかも知れないが、やはり幕府を憚り断念したのかもしれない。
なお生駒高俊の実子の項に、「母は某氏」、さらに実子の名が記載されていないことは、そもそも公式文書である『生駒家譜』に最初から記載する意味がないと考えられるが、後世削り取った可能性が高い。
また確認の意味で、光安から商家大井家に至る男系のなお以下に示す。
初代・大井光安、二代・楯岡長門守満廣、三代生駒高俊、四代・大井光長 そして商家初代・大井傳之亟となる。
光安を初代とした根拠は商家五代・大井光曙が文化年代に著した著書『二重櫻』で、武家が四代あ、そして元祖を光安としている事を参照した。
§6.鶴姫その人について
鶴姫の一生を振り返ると、典型的な戦国女性と言えよう。
想い起こされるのは、春日局である。
両者とも、幼少期に父が非業の最期を遂げている。春日局の父は明智光秀の重臣・斎藤利三で、本能寺の変後の山崎の合戦で敗れた後、捉えられ磔刑に処されている。
鶴姫の父は二章、三章に引用した文書にあるように、心ならずも自害に追い込まれている。
そして結婚であるが、春日局は母方の実家・稲葉氏の一族に、後妻として嫁し、鶴姫は父光安が領していた矢島の新領主舘岡長門守に嫁している。
これらの婚姻は両者にとって、子宝にも恵まれ、決して不幸なものではなかったが、彼女らの人生目標には家族の安寧に加えて父の怨念が常に心底にわだかまっており、その解消には子孫の隆盛以外あり得ないと思っていたのではなかろうか。
春日局は夫と離縁し、徳川三代将軍家光の乳母となり、その後は朝廷との折衝なども担い、女性政治家として活躍している。
また斎藤一族は敗戦後散りじりになるが、生き延びた者を稲葉一統の中に取り込んでいる。
その中から老中になった者もいる。象徴的なこととして、浪人していた元夫の稲葉正成は大名となっている。
一方鶴姫は長門守と死別したが、娘の一人は舘岡豊前守の養女となり、酒井家家臣・本城0氏初代の生母、さらにもう一名の娘を介し、大井光安の血統を後世に伝えている。
一族の非業の死を幼少期体験したことが、その後の人生の選択に大きく影響を与えた事は確かであろう。
戦国時代には政略結婚が親の指示で、ごく普通に行われていたが、両者は、自らの意思で“政略結婚”へ志向したように、筆者には思える。
戦国を生き抜き、一族の命脈を後代に伝えた両女性の強靭な生き方に、ただ刮目するのみである。
(平成31年3月25日了)
4 矢島満安の遺骨と由利十二頭記について
矢島満安の遺骨と由利十二頭記について
大井 益二
はじめに
戦国期由利地方に存在していた由利十二頭を記した古文書が、多数今日に伝えられている。
この中で矢島満安(大井光安)の記述内容に着目し、多数の文書を大別すると、次の二様に分類できる。
・A説:天正16(1588)年、荒倉舘落城後、仁賀保軍に討ち取られる。
・B説:文禄1(1592)年、西馬音内城にて自刃。
実在した人物の最期の状況および時期が、これほど異なって伝承されるケースも珍しい。
この二説の内容を両説併記の形式で『矢島十二頭記』の表題で、連続文としてまとめられたものが『続群書類従』に収録されている。
一方、満安の最期に関係する痕跡として、西馬音内城の自刃地の碑、菩提寺の墓碑が、伝承と共に今日に伝えられている。
本稿では先ず昭和17年、実施された満安墓所改葬で出土した頭蓋骨等にかかわる記録を紹介する。
次に『続群書類従・矢島十二頭記』の編纂背景について考察し、A説、B説の信憑性について言及する。
さらに由利地方に何故に同工異曲の「十二頭記」が、異常といってよいほど多数今日に伝えられているのかについて推量する。
最後に由利十二頭に発給されたとする「秀吉朱印状」について私見を述べる。
§1.矢島満安墓所改装記録と伝承について
平成も20年代に入った現在、満安の遺骨が現存している事を知っている人は案外少ない。
満安の菩提寺である矢島町立石・高建寺において、墓所改装が戦時下の昭和17年、18年の両年にわたり実施され、その折の記録が『大井満安公墓碑建設前後の事情』として、高建寺20世住職である佐藤儀孝氏により著されている。以下主要部分について転載する。
大井満安公の墓碑は現在位置の高建寺の墓地に存していた。特に現在位置といったのは、高建寺は現在の所に位置する迄には凡そ三轉もしているのである。最初は根城、次は坂之下、次は現在の所である。一説に依れば川内村伏見にあった事もあり、叉更に新しい一説には今の龍源寺の位置に高建寺があったとの話もある。兎に角轉々した事だけは確かである。然し此の碑が何れの時代に建設され、何れの麗所から移轉されたかは不明である。石の質は所謂川内石でもろく、それに長年の風化により刻んだ戒名も殆んど消滅、只下方に尊儀(貴人の尊称)の二字だけが微かに読まれる程度であった。然も元は完全な五輪の碑形を具へておったそうだが、明治廿七年の地震の際、頭部は落ちて微塵にくだけ台座も割れ、只棹石だけが無事であった。
その後ほんの間に合せの修理をして新碑建設直前迄存したのである。
ところが去年即ち昭和十七年春以來、高建寺墓地組合に依り同墓地全部の改修および区画整理工事が断行され、その際止むなく、公の墓碑も幾分位置の変更を餘儀なくされた。で改めて遺骨を埋葬するため、碑地下を深く掘り下げたところ、そこに公の遺骨を発見したのである。
頭蓋骨(腐朽完全ならず)、大腿骨の関節かと思はれるもの、その他二・三骨片及び棺の釘らしく、角にして長大なるもの数本(腐朽して不完全)等である。
棺か箱に納めたものであらうが勿論腐朽して何の跡かたも留めない。そこで暫くの間、これを新しい甕に納めて、寺内の霊廟に奉安しておったのである。
一帯、公の墓碑改建の事はそうした無惨な碑の姿を拜するにつけ當局者としては餘程以前からの希望でもあり、念願でもあったのである。
たまたま、本年昭和十八年は公の三百五十年遠諄に相当するので、之を機会に大法要を嚴修し且つは墓碑を樹立しようと云ふ議が寺檀の間に於てまとまり、先ず工事委員を決定、同委員としては常時現在の総代人茂木光三、三浦徳三郎、佐藤直千代、木村勇七、三浦甚兵衛以上五名の諸氏、外に三浦仁吉、茂木留治郎、木村明治郎、佐藤権之亟の諸氏である。 (以下略)
このほか記録には記されていないが、関係者の話として次の事項が伝えられている。
・頭蓋骨が大ぶりであったこと。
・出土直後は骨の色は白色であったが、短時間に淡い褐色に変色したこと。
・前頭部に刀痕が認められること。
・満安と姻戚関係にある、墓碑近傍の旧家三浦家の先祖が、西馬音内より夜陰に紛れて、遺骸を運んだとの家伝があること。
・同家では現在も満安の祥月命日である12月28日の供養が続けられていること。
この中で満安最期の状況を伝える物証は、頭蓋骨と大腿骨が一緒に出土していることであろう。
もし満安が、仁賀保勢に討ち取られたとするならば、首は戦勝の証として持ち去られるはずで、少なくとも再び胴体と一所になる事はきわめて考えがたい。
以上の事項は、ことごとく‘満安、西馬音内切腹説(B説)’を肯定するといってよい。
僅かに討ち死に説と矛盾しない事項は、「前頭部刀痕」であるが、これも介錯時のものの可能性があり、逆に壮絶な切腹であったとの伝承を裏づけるとも考えられる。
これに対し、満安が仁賀保軍との戦いで討ち取られたとするA説を裏付ける物証は無く、ただ古文書類が多数今日に伝えられているのみである。
なお本来であれば満安の埋葬地は菩提寺高建寺であるが、当時同寺は、現在の竜源寺(矢島町城内)の地にあり、当時ここ一帯は宿敵仁賀保氏の占領下であるところから、やむなく子吉川右岸の現在地となったものである。
その後打越氏が矢島領主となった折に、高建寺は坂之下に移転された。しかし程なく大洪水に見舞われ住職もろとも寺は流亡し、その後満安埋葬地である現在地に建立されたと考えられる。
以上記した事項により「西馬音内城にて自刃説」に疑義を挟む余地は、極めて少ないと推量される。
§2.『続群書類従・矢島十二頭記』について
これまで『矢島十二頭記』の掲載経過については次の様に考えられて来ている。
塙保己一主宰の「和学講談所」では『続群書類従・矢島十二頭記』の編集に当たっては、集めた十二頭記の数ある伝本写本の中から内容的に見て、二種類に分類できることに気づ、これを収載したとの説である。
なお同書の前段がA説、後段がB説となっており、両者はページを替えず、続き書きされている。
本稿では『群書類従』の編纂背景を踏まえつつ、以下考察する。
寛永17(1640)年讃岐高松より出羽矢島に転封された生駒氏と、元和9(1623)年再び常陸武田から由利に戻った旗本・仁賀保氏の間に、元禄2(1689)年、領地境界をめぐる争いがあり、その裁定が関係書類と共に幕府寺社奉行に持ち込まれており、翌元禄3年の裁許では生駒藩の勝訴で終着している。なお仁賀保ではこの論所を「冬師山・かじか沢論所」と呼びなしている。(古文書散歩第三集・矢島町教育委員会)
数年ほど前、和学講談所の嫡流であり、『群書類従正編』木の木版を保有し、今日なお刷り立て事業を継続している温故学会(東京・渋谷区)を訪れ、種々にわたり教示していただいた。
その中で、和学講談所(以下和学所という)と、幕府をはじめとする公的機関との関係について、次に示す内容がある。
「林大学頭をはじめ寺社奉行、町奉行、あるいは大名等の配慮と援助は、和学所への経済的援助にとどまらず、古書・古文献の調査収集など、あらゆる面に及んでいる。」
この中には、幕府関係機関(奉行所等)が管轄していた裁判や訴訟記録の一部も、和学所・塙保己一のもとに提供されている。
例えば、南町奉行・大岡越前守忠相時代の裁判記録で、「小笠原諸島は我が先祖が文禄2年に発見した」と主張した小笠原貞任を、「出自詐称した者」として、享保20年、罪科に処した記録が、そっくり和学所が所収している。(温故叢誌第59号-温故学会)
この様な事情を踏まえ『矢島十二頭記』を改めて読み直すと、矢島満安の最期を天正16年討ち死にとした前段文(A説)、文禄元年切腹とした後段文(B説)ともに支配地領有の変遷に力点を置き記述されていることに気がつく。
特に訴訟攻防の焦点となっている‘ブナノキフチ(地名)’の箇所は、両者さり気なくかつ抜け目なく自領であることを記している。
仮に『矢島十二頭記』が評定資料であるとすれば、生駒勝訴であるので幕府は後段文(B説)を是とした事になる。
それはともかくとして『矢島十二頭記』が訴訟資料であることを裏付ける事として、前段文後段文が用紙を改めず続け書きされた、不離一体となっていることが挙げられる。
もし別々に所収したとするならば、それぞれに入手先の名が記されていなければならないと考えるからである。
ちなみに『群書類従正編』の各本の奥書には、入手先の名が記されている事が多く、この事から借用書あるいは譲渡物の一次筆者の段階では先方の名は特に事情がない限り書き込まれたと考えられる。
言い換えると、借覧先の名が記されていないということは、和学所で清書された物ではなく、原本そのものが譲渡された可能性が高い。
また膨大な書類を保管している奉行所等の機関からの譲渡であれば、その量も和学所にとっても膨大であったはずで、いちいち先方の名を記すことの煩雑さを避けるため、取りあえずは専用コーナーに収蔵し、掲載が決まった段階で先方の名が付されたと考えられる。
以上の理由から『矢島十二頭記』は、生駒、仁賀保両家から奉行所に別々に証拠として提出された書類の可能性が高く、奉行所においてそれらをまとめて筆写し、改めて両家に下げ渡し、評定の際の証拠資料としたものと考えられる。
また続け書きした理由は、紙数の節約や散逸の防止等ではなく、後日の改竄等の防止するため、現代の契約書などに見られる‘割印’の機能を持たせたものであろう。
もし『矢島十二頭記』が、塙保己一が手ずから編集した群書類従正編(木版、文政2年完了)に収録されたと仮定すれば、両説併記とせずに、吟味の上一説に絞り込んだはずである。
なぜなら、『群書類従』の購読者は幕府、大名、旗本、豪商さらには寺社等であり、価格も高価であり二節併記の様な曖昧な形で、販売することはありえないと考えられるからである。
しかしその二年後、『群書類従』の続編の発行に心を残しつつ彼が死去してからは和学所の事業は低迷する。
そして慶応3年に和学講談所そのものが幕府と共に消滅するが、膨大な文書資料が、混乱のさなか紆余曲折を経て、後世に残される。
その過程で《矢島十二頭記》の様に入手先の記名がないものは、出自不明となったものであろう。
また別の可能性として、幕府等からの譲渡であれば、その名を記す事は憚られたとも思え、それを補完する措置として『矢島十二頭記』の冒頭に「総検校 保己一集」と官職名を記し、‘官から官へ’を滲ませたとも思える。
そして明治期に入り、渋沢栄一等の後援により、『続群書類従』として編纂事業が再開され、昭和40年代になって完了している。
木版から活版印刷の時代となり、大量の文書処理が可能となったことから、編集方針は内容の吟味した少数精鋭主義ではなく、玉石混交を許容し、多量の文献を後世に伝える事を目的としている。以上が筆者が考える『矢島十二頭記』が続『類従』に収録された経緯である。
ところで『矢島十二頭記』の名称であるが、内容から命名するとすれば、‘矢島仁賀保争乱記’あるいは単に‘矢島仁賀保記’とすべきと思われるが、『群書類従』の編纂事業時には、旗本・仁賀保氏が健在であり、かつ筆耕者の大半は旗本の二、三男であるが、中には出羽亀田藩主もいたことから、‘仁賀保’の三文字が目立つことは憚られたと思われる。
そんな事情からか、一歩引いた表現とし、‘仁賀保’に代わる固有名詞として旧称の「小笠原、大井」などが候補として浮んだと思われる。
しかし前二者では、「矢島小笠原記」「矢島大井記」となり、これでは矢島大井氏のみの記録と誤解されかねないと考え、塙保己一自信も、しっくり来ない事を感じつつも、止むなく仁賀保の代名詞として「十二頭」を暫定的に選択したように思える。
また満安の最期年であるが、西馬音内切腹説の古文書は、ほぼ文禄元年と記されており、肯定されるべきと考えている。
なお元禄期、戸部正直により著された『奥羽永慶軍記』の満安最期を‘文禄二年’となっている箇所があるが、前後の関連記事から明らかな誤植であることがわかる。
§3.十二頭記の伝本写本が多数存在することについて
次に§1で紹介した「遺骨出土」という確かな物証が存在するにもかかわらず、「何故に同工異曲の内容の伝本写本とりわけA説仁賀保有利本が数多く今日に伝わっているのか」との疑問について考えてみたい。
生駒藩は後段文(B説)を添えて評定に臨んだと思われるが、これに対し仁賀保家も何らかの反証の古記録等が必要となったはずである。
しかし常陸武田に国替えになった際、由利時代の関係書類は必要最小限のもの以外は処分したであろうし、よもや再び由利に戻るとは思いもかけなかったであろう。
しかし、このままの文書証拠皆無の状態では勝訴はおろか、何の根拠もなく他藩の土地を不法占拠していた事になり、幕府の心証次第では敗訴に留まらず、更なるペナルティを受けかねないとも案じたかも知れない。
ではどうすべきか、恐らく仁賀保有利の文書(前段文)を作成し、幕府に提出すると同時に自領および周辺の寺社や旧家に所蔵を依頼し、幕府検使(原五兵衛、服部千右衛門)が現地確認に来訪の際、さりげなく紹介し、既提出文書の内容が、地元に古くから伝わっているものであることを印象付けようとしたのではないだろうか。
仁賀保文書の種本は生駒提出のものであったと推量されるが、それでも一縷の望みは、天正15年12月に、豊臣政権により発令された惣無事令以後の私闘が、後段文には多く記されている点を衝き「発令後の合戦はないはず」との論理展開に持ち込み、一発逆転を狙ったものとも考えられる内容である。
以上述べた事が、正鵠を得ているとすれば、これら処々に配布された文書は時とともに、その経緯は忘れ去られ、真っ当な‘古文書’として光を放ち始め、旧家によっては、それに自家の先祖の事跡を加え、家由来書として今日に伝えているケースもあると思われる。なお前段文と同内容の昭和56年公開の仁賀保家文書(福井市久津見成美氏所蔵、現仁賀保市所有)の由利十二頭記は、その奥書によれば「天明八(1788)年、須田権左衛門出府之節持参し、翌四月写本したものである」と記されている。
この時期、和学所はその前身である塙主宰の「温故堂」が既に設立され、出版事業も始まっている。
従って『矢島十二頭記』は既に奉行所より収集されていたと思われ、その内容に現役の旗本である仁賀保家の先祖が記述されており、当然のこととして塙は確認のため、同家に連絡したはずである。
再び由利を知行地としていた仁賀保家は、元禄の頃より由利地方の旧家等に所在していた文書を捜索し、発見したものを、須田権左衛門に持参させ、温故堂に出向き『矢島十二頭記』との照合に供したものと考えられる。
一方、生駒家と和学所の接触は文化元年、塙検校が時候の挨拶の折、矢島九代親章(文化14年、45歳没)に参上した記録があり、日ごろから親しい関係にあったことから『矢島十二頭記』の内容について話題としたことは確かといってよいであろう。(生駒藩・御納戸日記第三集-矢島町教育委員会)
塙は生駒勝訴と、A説の稚雑さ(秀吉が関白時代の記事に太閤の呼称を用いる等)を考え合わせ、B説後段文が事実であると考えていたと推量される。
§4.秀吉朱印状への疑義
ところで、秀吉名の由利十二頭に宛てた朱印状(日付はすべて天正18年12月24日)の写し及び真筆とされる仁賀保、打越等へ宛てた秀吉朱印状も現存している。
しかし、これらについては次の疑問に明確に答えて初めて史料として参考にすべきであろう。
(1)天正18年文書の筆写者の特定と伝承状況について
これらの写し書を所有していても不自然でないと考えられるのは、給付者である豊臣政権か、発給された朱印状を由利国人集に仲介したと思われる最上義光かの二者であることは自明である。
炎上した大阪城に拠っていた豊臣政権は論外であるが、しかし最上氏も程なく改易されているので、これらの朱印状の写しが、まとまって後世に伝承されたとする説に依拠する場合は、今日への伝承経過についての考察が不可欠である。
(2)仁賀保市所有の秀吉朱印状が一所に存していたことについて
同氏の所蔵していた朱印状は仁賀保氏と打越氏等に宛てた3通で、真筆とされるこれらが一所に存することは、常識的に考えるとあり得ないことと思われる。
これらの朱印状が本物であったとすれば、元禄期の訴訟において仁賀保家は証拠として、当然提出したと思われ、資料の種別として、絶対的なものであるだけに、仁賀保勝訴の裁定に至ったはずである。
しかしながら仁賀保敗訴であるので、朱印状は本物と認定されなかったものと思われ、あるいは仁賀保家はその信憑性に自信が持てず、未提出としたと思われる。
いずれにしても、ここ一番で真価を発揮することが役割である朱印状が、内外から評価されなかった事実はきわめて重要なこととして認識しておく必要がある。
本物か否かはひとまず置くとして、ではなぜ豊臣政権による領地あてがいの朱印状の写しや仁賀保氏と打越氏等への真筆とされる朱印状が今日に伝わったのかとの疑問が残る。
恐らく仁賀保家は前に記した前段文を作成頒布したことと同様の意図で作成し、ただ配布先が旧家等ではなく、それらを所持していたとしても不自然ではない由利十二頭の末裔を考えていたものと思われる。
しかし前段文はただの‘古文書’であるが、朱印状は現代風にいえば‘有印公文書’であり、偽造であることが判明した場合「お上を怖れぬ所業」となり、ただではすまないと危惧し、作成まではしたものの配布には至らず、一所にまとめてお蔵入りとなり、明治維新の混乱した時世に流出したのではないかと推量される。
以上が筆者の考えている「秀吉朱印状」がまとまって存在していた理由である。
なおこれらの文書の作成に当たって、仁賀保家は入念な調査を実施したはずで、その詳細内容については、一部を除いて正鵠を得ていると思われ、その意味で資料的な価値は有している可能性は高い。
あとがき
筆者が矢島満安に興味をもったのは、あまりに多くの十二頭記が存在し、当家の土蔵からもその一つが発見されたことに始まる。
そしてその記述形式が、押しなべて箇条書きであり、おもしろおかしく書かれた読み本ではなく、何らかの目的あるいは作為が背景にあると感じたことにもある。
検討作業の端緒として『群書類従』の原版を継承し今日なを刷り立て事業を継続している「温故学会(東京・渋谷区)」を訪ね会長の斎藤政雄氏に種々教授して頂いた。
その中での注目すべきこととして本文でも触れたが、裁判、訴訟関係の資料が、和学講談所塙保己一のもとに提供されている事実があった。
このことから『矢島十二頭記』も訴訟資料の一部ではないかと考え、生駒藩の記録を調べたところ、仁賀保家との山論に辿りつき、仮説を構築する事ができた。
そして多数の『由利十二頭記』の存在および『秀吉朱印状』が一所に存在していた事の、一応説明できたと考えている。
これらの論旨の出発点は言うまでもなく、「満安遺骨の出土」である。
なお本稿では‘満安’として記述して来たが、これは西馬音内に逃れた後、‘大江満安’と名乗った時期があり、その名残として伝承されたことに由来する。(赤宇津大井家文書-岩城町資料館所蔵)
従って‘満安’の出現は、地域的には西馬音内方面、時代的には晩年になるほど多い。
しかし名前にとどまらず姓まで変えているところから、仮名として一時的に名乗ったとも考えられ、旧領矢島を奪還した暁には、再び‘大井光安’に復したと思われる。
ところで、余談となるが、明治9年、日本とアメリカ、ロシア、イギリスの間で、小笠原諸島の帰属が問題になった際、その帰趨を決定づけたのが前記した享保時代に作成された小笠原貞任裁判記録である。
今日から思うと、群書類従編纂事業より生じた最大価値と言ってよく、また国益に貢献した最大級の古文書であると思われる。
あくまでも架空の話であるが、名奉行の誉れ高い大岡越前守忠相が生前もしこの事実を知ったとしたら、彼は潔く自決したものと思う。
何事によらず歴史の風雪に耐えることの難しさをかみしめつつ稿を終える。
(平成23年09月30日了)
マップ
秋田県由利本荘市矢島町舘町59
大井家住宅
おおいけじゅうたく
Oikejutaku Cultural property